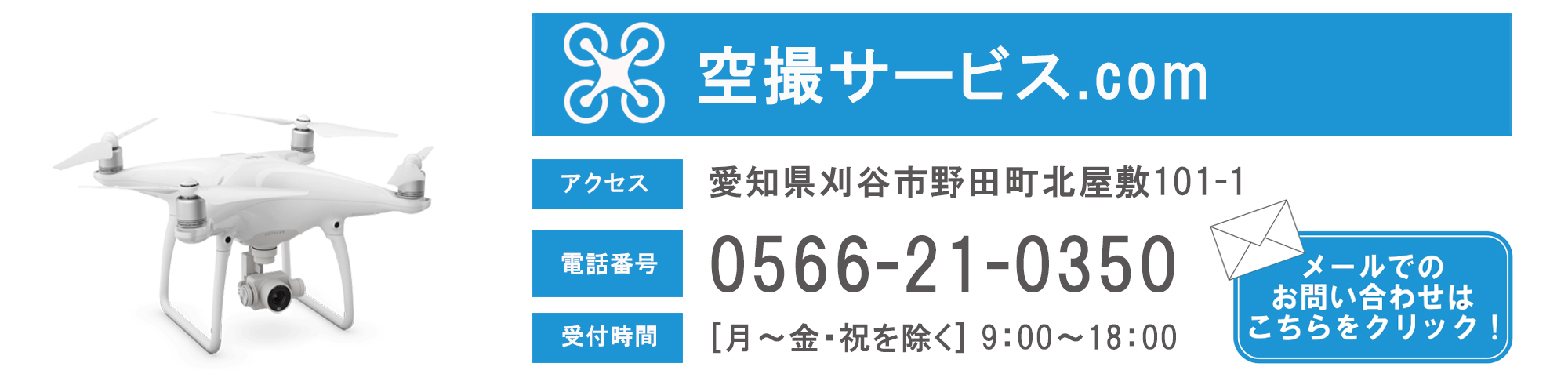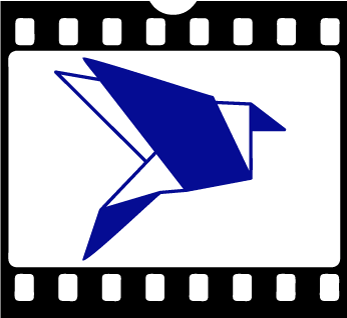空撮ギャラリー
>へきなん広報大使 中村優花が聞く!愛知県 老朽化橋梁との戦い!
愛知県高浜市と半田市を結ぶ衣浦大橋の疲労き裂対策として実施されたSFRC舗装工事。
愛知県が管理する橋梁は5000橋あり、その橋一つ一つに対して調査、補修をしていくこと。
その大切さを碧南広報大使の中村優花さんが聞いていく動画になります。
- 撮影日時:2023年
- 撮影時間:―
- 撮影場所:愛知県内
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:否
いちから分かるSFRC舗装工事 ~衣浦大橋の疲労き裂対策を題材に~
愛知県高浜市と半田市を結ぶ衣浦大橋の疲労き裂対策として実施されたSFRC舗装工事。
そもそもSFRCってなにということから、実際にSFRCの施工紹介動画になります。どちらかというと一般の方向けではなく。
実際にSFRCを施工管理する方に向けて作成しました、ナレーションは碧南広報大使の中村優花さんが担当しております。
- 撮影日時:2023年
- 撮影時間:―
- 撮影場所:愛知県内
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:否
加木屋架道橋架設工事【多軸移動台車による夜間一括架設】の紹介【FULLver.前半】
2023年1月27日 東海市加木屋町 ニールセンローゼ橋の架設動画を撮影させていただきました。 当日は朝から雪が降る、悪天でした. この動画は、夜間架設までの動画になります。
- 撮影日時:2023年1月27日
- 撮影時間:―
- 撮影場所:東海市加木屋町
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:否
加木屋架道橋架設工事【多軸移動台車による夜間一括架設】の紹介【FULLver.後半】
2023年1月27日 東海市加木屋町 ニールセンローゼ橋の架設動画を撮影させていただきました。 当日は朝から雪が降る、悪天でした. この動画は、夜間架設からの動画になります。 夜間一括架設から最後に両端部を架設するまでの動画になります。
- 撮影日時:2023年1月27日
- 撮影時間:―
- 撮影場所:東海市加木屋町
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:否
名鉄河和線 東海市加木屋町 ニールセンローゼ橋
2023年1月27日 東海市加木屋町 ニールセンローゼ橋の架設動画を撮影させていただきました。 当日は朝から雪が降る、悪天でしたが、夜間の多軸移動台車による架設の際は、雪もやみ撮影ができました。 20時から始まった夜間架設は翌日の5時半に作業完了しました。こちらはショート版になります。 ロング版は現在製作中になります。
- 撮影日時:2023年1月27日
- 撮影時間:―
- 撮影場所:東海市加木屋町
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:否
衣浦大橋台船架設動画
衣浦大橋にかかる三本目の橋の台船架設を撮影させていただきました。
- 撮影日時:2023年1月~2月
- 撮影時間:―
- 撮影場所:衣浦大橋付近
- 撮影機材:―
- 素材販売の可否:不可
動画編集
動画撮影から編集まですべて弊社で行うことが可能となります。
動画撮影もドローンを使ったものから地上で一眼レフやスタビライザーを用いた映像も撮影可能となります。
また撮影内容も、モーションロゴの作成からカラーコレクションの実施、エフェクトの追加まで全て行えます。
声優を利用したナレーションの追加やアニメーションの追加等も承っております。
企画段階からの脚本も現役の放送作家を踏まえての打合せも可能となっております。
動画撮影から動画編集、ナレーションの追加まで、納品後即youtube等に使うことができます
| 動画編集<尺によって変更します> | 50,000円〜 |
|---|